記事概要
- 僕がよく使用するif文の使い方をまとめます
- 基本記法
- 複数の分岐
elifelse - 複数の条件
andor
サンプルコード
a = 10
if a % 2 == 0:
print("aは偶数")
b = 3
if b % 2 == 0:
print("bは偶数")
elif b % 2 != 0:
print("bは奇数")
c = 5
if c % 2 == 0:
print("cは偶数")
else:
print("cは奇数")
d = 9
if d % 2 == 0 and d % 3 == 0:
print("dは2と3の倍数")
elif d % 2 == 0 and d % 3 != 0:
print("dは2の倍数")
elif d % 2 != 0 and d % 3 == 0:
print("dは3の倍数")
else:
print("dは2の倍数でも3の倍数でもない")
e = 4
if e % 2 == 0 or e % 3 == 0:
print("eは2の倍数または3の倍数")実行結果
aは偶数
bは奇数
cは奇数
dは3の倍数
eは2の倍数または3の倍数if文の基本
記法
if 【条件文】:
処理内容- 条件時に処理させたい内容はインデントを一つ下げる
- 下げないとifの条件に関わらず処理されるので注意
コード例
if条件が該当する時
a = 10
if a % 2 == 0:
print("aは偶数")結果
aは偶数if条件が該当しない時
a = 9
if a % 2 == 0:
print("aは偶数")結果
```
(何も出力されない)
## 複数の分岐の場合
`if~elif~else`を使用する
```python:
if 【条件文①】:
処理①
elif 【条件文②】:
処理②
else:
処理③- `elif`は複数入れられる
- `else`はなくても良い
- ただし、システムに使用する場合、条件漏れの判定はしたほうが良いため、プログラム的には合ったほうが良い
コード例
下記2つは同じ意味を持つ
b = 3
if b % 2 == 0:
print("bは偶数")
elif b % 2 != 0:
print("bは奇数")c = 5
if c % 2 == 0:
print("cは偶数")
else:
print("cは奇数")実行結果
bは奇数
cは奇数複数の条件
if文一つに対して、複数の条件を用いたい時は`and`や`or`を使用する
- `and`→〇〇かつ△△
- `or`→〇〇または△△
and:〇〇かつ△△
複数条件全てを満たしている場合に処理をする
if 条件① and 条件②:
処理内容- この場合は条件①、②両方満たしている場合に処理が行われる
- さらに条件を増やしたい場合は and で追加可能
コード例
d = 9
if d % 2 == 0 and d % 3 == 0:
print("dは2と3の倍数")
elif d % 2 == 0 and d % 3 != 0:
print("dは2の倍数")
elif d % 2 != 0 and d % 3 == 0:
print("dは3の倍数")
else:
print("dは2の倍数でも3の倍数でもない")実行結果
dは3の倍数or:〇〇または△△
どれか一つでも条件を満たしている場合に処理する
if 条件① or 条件②:
処理内容- この場合は条件①、②どちらかに該当する場合に処理が行われる
- さらに条件を増やしたい場合は or を追加できる
コード例
e = 4
if e % 2 == 0 or e % 3 == 0:
print("eは2の倍数または3の倍数")実行結果
eは2の倍数または3の倍数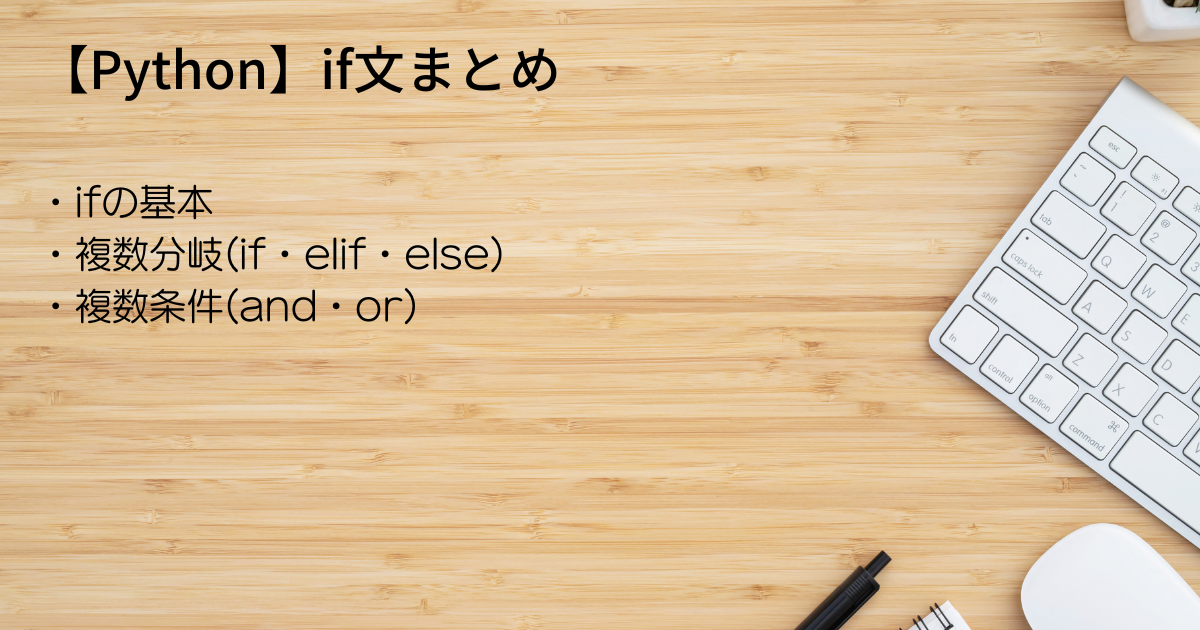


コメント